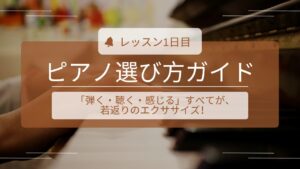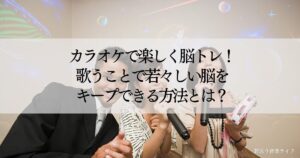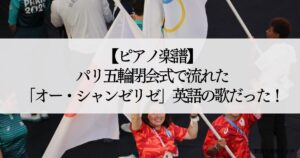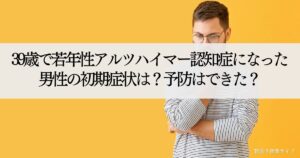「音感がいいね!」なんて言われたことはありませんか?
音楽を楽しむうえで欠かせないのが「音感」ですが、実は音感には「絶対音感」と「相対音感」という2種類があります。
この記事では、音感の基本から、絶対音感・相対音感の違い、どちらが身につけやすいのか、そして大人になってからでも音感を鍛えられる方法について、わかりやすくお届けします。
音楽初心者の方や、ピアノや歌をもっと楽しみたい方もぜひご覧ください♪
絶対音感と相対音感とは?それぞれの特徴を解説

絶対音感とは?
絶対音感とは、音を聴いただけでドレミの音名がわかる能力です。
ピアノの音を一音鳴らしただけで、「これはソの音!」と判断できるような感覚です。
幼少期に音楽教育を受けていると、この能力が育ちやすいと言われています。
絶対音感のメリット
- 楽器のチューニングがすぐできる
- 複雑な曲でもすぐに耳コピできる
- 楽譜がなくても演奏できることがある
相対音感とは?
相対音感とは、ある基準音(例えばド)を元に、他の音の高さを判断する能力です。
例えば「この音はドだから、次の音はミだな」と音の“間隔”で音名を推測します。
多くの人が大人になってから身につけられる音感です。
相対音感のメリット
- 音の高さだけでなく、和音の響きやメロディ全体を感じ取れる
- コーラスやアンサンブルで役立つ
- 作曲や即興演奏にも強くなる
絶対音感と相対音感、どちらが大切?

どちらも音楽にとって大切な能力ですが、音楽を楽しむうえで万能なのは相対音感と言われることが多いです。
プロの音楽家でも相対音感が重要?
実は、プロの演奏家や作曲家の中には「絶対音感はないけれど相対音感で十分」という人もいます。
演奏や合奏の現場では、「周囲と合わせる力」が求められるため、相対音感が活躍する場面が多いのです。
大人でも相対音感は鍛えられる!
相対音感は、音楽理論や聴音のトレーニングで身につけることができます。
ピアノやボーカルレッスンでも、相対音感を意識した指導が行われることが増えています。
音感を鍛えるためのトレーニング方法
相対音感を伸ばす練習方法
- ドレミを声に出して歌う:メロディを歌いながら音名を言うことで、音の間隔を感覚的に覚えます。
- 簡単な聴音トレーニング:ピアノの2音を聞いて、その音程差(例:ドとミなら「長3度」)を答える練習。
- ハーモニーを聞き分ける練習:和音の種類(メジャー、マイナーなど)を聴き取るトレーニングも効果的です。
\ドレミで歌う練習に最適/
絶対音感を身につけるのは難しい?
絶対音感は、3~6歳頃の音楽環境によって育つと言われています。
大人になってから身につけるのはかなり難しいですが、近い能力を鍛えることは可能です。
まとめ:音楽ライフに必要なのは「相対音感」かも?
「絶対音感がないと音楽はできない…」と思っていた方、ご安心ください。
むしろ、多くの人にとって実用的で身につけやすいのは「相対音感」です。
日々の練習やちょっとしたトレーニングで、あなたの音感はどんどん磨かれていきます。
音楽をもっと楽しみたいあなたも、「若返り音楽ライフ」で一緒に音感トレーニングをはじめてみませんか?